保育園年中
『最近、言葉づかいが悪くなって…』との相談。①幼児期の言葉は、圧倒的に家庭で保護者から学ぶ。保護者の言葉づかいに問題なければ、心配なし
②実は、適切な言葉も成長しているが、不適切な言葉は目立つので、多く使用と感じる
③『新しい言葉を使ってみたい』という知的好奇心— ひだ ゆう🎍発達相談員(幼児) (@Zteacher2017) September 19, 2021
保育園年中
『最近、言葉づかいが悪くなって…』との相談。
①幼児期の言葉は、圧倒的に家庭で保護者から学ぶ。保護者の言葉づかいに問題なければ、心配なし
②実は、適切な言葉も成長しているが、不適切な言葉は目立つので、多く使用と感じる
③『新しい言葉を使ってみたい』という知的好奇心
本記事では、現役の発達相談員で、元保育者の僕が。
幼児の「心配な言葉づかい」について。
どのように考え、対処したら良いか、お答えします。
【僕の簡単なプロフィール】
保育者として20年。その後、地域の発達相談員と幼稚園・保育園巡回の経験が15年ほどあり。
大学院では保育や教育の心理学(学校心理学)を専攻していました。
大学の専攻科では乳幼児の言語発達について専門に学びました。
所持資格:公認心理師(国家資格)、幼稚園教諭、小学校教諭など
記事の内容
1.【子ども】言葉づかいが悪い【直し方】

基本的な考え方は以下の3つです
①幼児期の言葉は、圧倒的に家庭で保護者から学ぶ。保護者の言葉づかいに問題なければ、心配なし
②実は、適切な言葉も成長しているが、不適切な言葉は目立つので、多く使用と感じる
③『新しい言葉を使ってみたい』という知的好奇心
それぞれ解説しますね。
①幼児期の言葉は、圧倒的に家庭で保護者から学ぶ。保護者の言葉づかいに問題なければ、心配なし
言葉は言葉づかいを含め、身近にいる人から学び。中でも主に養育している親から圧倒的に学びます。
子どもが地域の方言を自然に覚えるのはその為です。
ですので、一時期、適切でない言葉を使っていても。
普段の親の言葉づかいさえ問題なければ、心配ありません。
②実は、適切な言葉も成長しているが、不適切な言葉は目立つので、多く使用と感じる
使って欲しくない言葉を何度か聞くと、「そういう言葉ばかり使っている」ような気がします。
しかし、冷静に聞いてみると今まで話していなかった適切な言葉も使っているはずです。
言葉に限らず、心の成長の過程には、一時的に不適切な部分も同時に伸びていきます。
③『新しい言葉を使ってみたい』という知的好奇心
知的好奇心が高まってくると、いろいろな言葉を使ってみたくなるものです。
絶対に使って欲しくない言葉(人を傷つけるような言葉など)以外は、基本は「聞き流し」でもいいと思います。
周囲が反応しすぎると面白がって繰り返し使いたがるかも知れません。
そして、親が適切な言葉で返してあげると良いです。
2.悪い言葉づかい【3種類の対応方法】

幼児の不適切な言葉は3種類あり、対応も違うと考えます
①うんち、おしり等、好奇心の言葉
②お前、コノヤロウ等、相手を攻撃の言葉
③太ってるー等、状況判断できない言葉いずれも指導は必要だが、
①→基本は無視
②→子の状況にストレスあるならそこに対応
③→相手の気持ちや場の状況を教える— ひだ ゆう⛄発達相談員(幼児) (@Zteacher2017) November 21, 2021
幼児の不適切な言葉は3種類あり、対応も違うと考えます
①うんち、おしり等、好奇心の言葉
②お前、コノヤロウ等、相手を攻撃の言葉
③太ってるー等、状況判断できない言葉
いずれも指導は必要だが、
①→基本は無視
②→子の状況にストレスあるならそこに対応
③→相手の気持ちや場の状況を教える
それぞれ解説しますね。
①うんち、おしり等、好奇心の言葉
「うんち」「おしり」など、人を傷つけないけど、好奇心で面白がって使う場合が多くあります。
周りの幼児がゲラゲラ笑って反応があると、子どもはなおさら使いたくなるものです。
基本は無視(見て見ぬふり)でいいと思いますが。
頻繁に使っていたり、食事中などその場には適切でないような場合には、毅然と注意してもいいと思います。
②お前、コノヤロウ等、相手を攻撃の言葉
普段そのような言葉を使っていなくても。
行動・活動を静止されたり、大人からの注意が多くなったりすると乱暴・攻撃的な言葉を発する場合が幼児でもあります。
その子なりのストレスの表現である場合もあります。
その場合には、単にその言葉を使わないようにさせるのでは根本的な解決にはなりません。
ストレスの基となっていることを考え、そこに対処する必要があります。
③太ってるー等、状況判断できない言葉
「ふとってるー」など、悪気がないのに相手が嫌がるような言葉を使う場合があります。
まだ、相手の気持ちに気付けない場合もあるので。
その場合には、相手は嫌な気持ちになることを伝え、具体的に相手の気持ちに気付かせることが大切です。
3.親の感情的な言葉(まねして欲しくない言葉)をまねしたとき
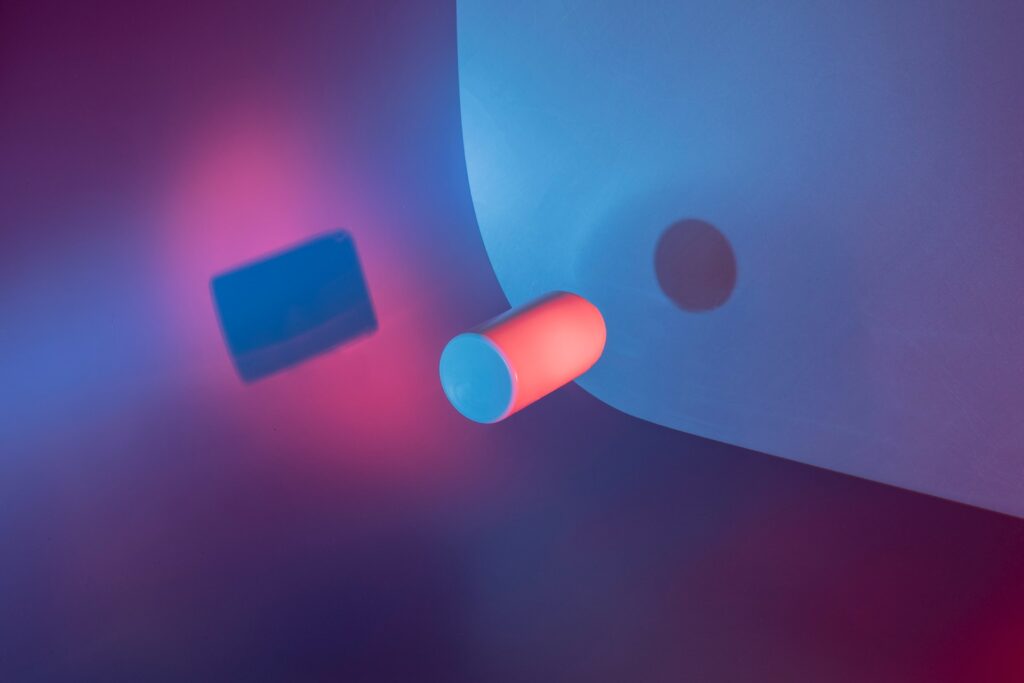
幼児の言葉は親の言葉をまねして成長しますが。
言葉の奥にある感情(思い)も一緒に伝わります。だから。『つい、感情的に使ってしまった、まねして欲しくない』言葉も。
「こんな言葉を使ってしまって、ごめんね」という思いさえあれば。その“思い”も、あとから子供には伝わるものだと思っています。— ひだ ゆう🍰発達相談員(幼児) (@Zteacher2017) May 11, 2022
親も人間です。気持ちに余裕のないときに。
つい、「まねして欲しくない」「感情的な言葉」を発してしまうことがあり。
そして、その言葉を子どもがまねして使う場合があります。
冷静になったとき「こんな言葉を言ってしまった。ごめんね。」という思いがあり。
その後もそういう育て方をしていれば。
その気持ちは子どもにも伝わり。
将来、子どもに言葉を使う判断力がつけば、そういう言葉は使いません。
4.まとめ:【子ども】言葉づかいが悪い【直し方】

言葉の成長期である幼児期。
適切な言葉と同時に使って欲しくない(適切でない)言葉も同時に増えます。
繰り返しますが、親が日常的に不適切な言葉を使っていなければ基本的には問題ありません。
不適切な言葉は目立つので、「そんな言葉ばかり使っている」と錯覚しがちになります。
度を過ぎた場合には、注意することは必要ですが。
使って欲しくない言葉を聞いたら、
①基本的には無視(見て見ぬふり)し、
②親が適切な言葉を使い、
③子どもが適切な言葉を使っているときに褒めてあげる、
でいいと思います。


